
税理士 大河原真吾
東京税理士会麴町支部 登録番号:153981
この記事の執筆者:税理士 大河原真吾
一般家庭の相続税申告とオーナー経営者の事業承継・相続税申告に豊富な経験を持つ。特に土地の相続税評価額の減少と事業承継のスキーム構築を強みとする。お客様の意向を最大限に尊重したオーダーメイドなサービスを提供し、適正な料金でお客様に寄り添うことをモットーとする。
「相続人等の売渡請求」を定款に定めることで、自社株の分散を防ごうとするケースが増えています。しかし、この制度にはメリットばかりではなく、見過ごされがちなリスクも潜んでいます。今回は、相続人等の売渡請求にまつわる潜在的なリスクについて掘り下げてみましょう。
目次
(1)相続人等の売渡請求とは?
まず、相続人等の売渡請求について簡単に触れておきます。これは、会社が定款に定めることで、株主が死亡した場合にその相続人が取得した株式について、会社が相続人に対して売渡しを請求できる権利です。これにより、意図しない第三者への株式分散を防ぎ、安定した経営体制を維持することを目的としています。
少数株主が多い非上場会社では、支配権の強化の為に少数株主から株式を買い取る試みがされますが、買取りに応じてくれない株主も少なからずいます。
その場合、その株主に相続が開始しその相続人が取得した株式について売渡しを請求できるので効果は非常に高いです。
しかし多くのオーナー経営者が次のリスクがあることを認識していません。
(2)オーナー経営者の相続発生時に乗っ取りに使われるリスク
株主が死亡した場合にその相続人が取得した株式について、会社が相続人に対して売渡しを請求できるという事は、当然、自社株の分散を防ぐために「相続人等の売渡請求」を定款に定めたオーナー経営者の相続人にも適用されます。
たとえば、67%の株式を有するA氏と、33%の株式を持つB氏がいたとします。ある日A氏に相続が発生した場合、A氏の相続人は、会社から株式を売り渡すように請求される可能性もあります。
何故、そんなことが起きるのか?
それは相続人等に対する売渡請求は、株主総会の特別決議が必要ですが、買い取り対象となっている株主は、相続人等に対する売渡請求にあたって議決権を持たないからです。
※特別決議とは、株主総会における決議方法の一つで、会社の重要な意思決定を行う際に用いられます。具体的には、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
A氏の相続が発生した場合の相続人等に対する売渡請求に係る特別決議の要件
要件1
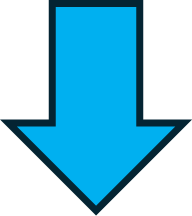
要件2
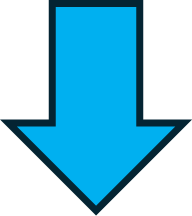
A氏の相続人は、B氏の議決権行使により会社からの売り渡し請求に従わざるを得ないこととなります。
(3)リスクを軽減するために考えられる対策
①オーナー経営者以外の株式以外の株式は、売渡請求についての議決権を制限しておく
相続人等に対する株式の売渡請求の議案について、の株主の株式について議決権制限種類株式としておくことによりリスクを回避できます。
ただし、変更には、特別決議が必要となりオーナー経営者とその推定相続人等だけで2/3以上の議決権を有していない場合、変更は極めて困難です。また、2/3以上の議決権を有していても剰余金の配当優先を付加する等の対応がないと少数株主との合意は困難です。また合意が出来ても配当により資金が社外流出します。
②オーナー経営者の株式を資産管理会社に渡しておく
オーナー経営者の株式を保有するための法人を設立し、オーナー経営者の株式を保有させておく方法です。この方法によれば、そもそもAが亡くなっても、相続による承継自体が生じないので、売渡請求についての決議では、法人が議決権を行使できます。
ただしオーナー経営者の株式を法人に保有させる場合、法人には株式の買取り資金の用意が必要です。買取り資金を借入で調達する場合、返済原資を株式の発行法人からの配当で充てれば、税務上の優遇措置もあります。
ただ、発行法人が、多額の配当をする事により株式の相続税評価額が高くなるリスクもあり、シミュレーションが必要となります。
また、オーナー経営者は株式を法人に売り渡す事による譲渡所得税の納税が必要になり、売り渡す株式の時価評価も必要になります。
まとめ
相続人等の売渡請求は、少数株主に相続が開始しその相続人が取得した株式について売渡しを請求できるので効果は非常に高い反面、乗っ取りリスクを含んでいるため、対策が必要となります。ただ乗っ取りリスクに対して決定的な回避方法がないのが現状です。
現実的な対応としては、会社の状況により異なりますが、即効性がある上記「オーナー経営者の株式を資産管理会社に渡しておく」方法と低コストである少数株主の相続が開始するたびに地道に買い進める複合的な対応が必要となります。
弊所は、麴町駅から徒歩1分にあり、事業承継税制、オーナー経営者の相続税対策について実績が豊富にございます。また、初回相談60分無料で、WEB相談も可能です。
事業承継でお困りの際は、ご相談ください。







